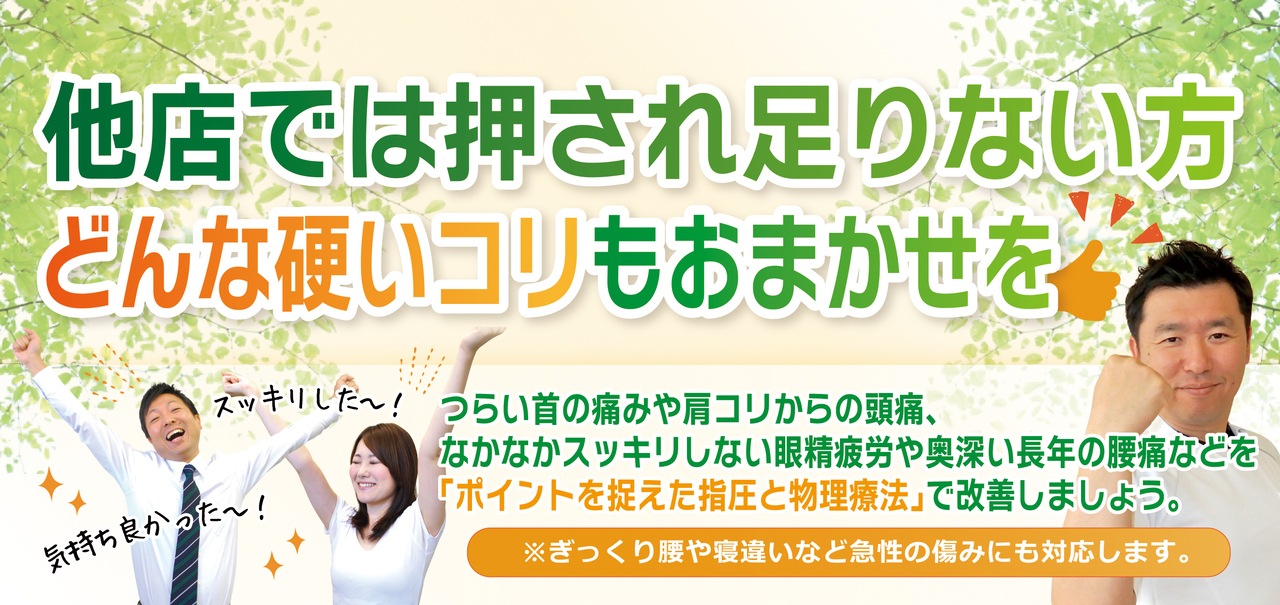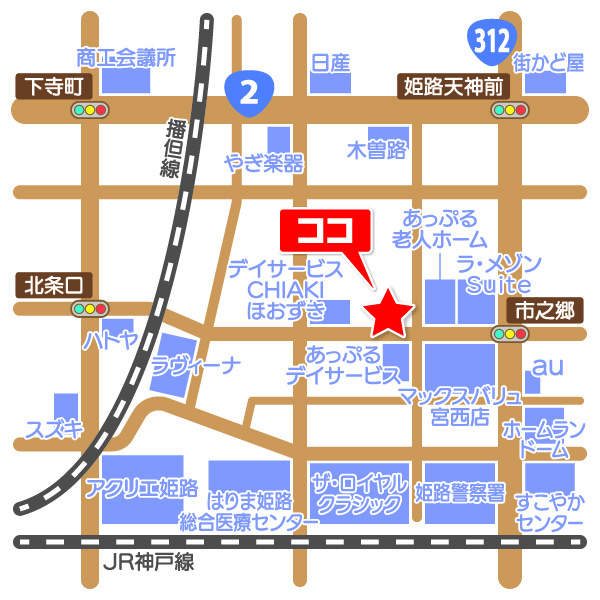不眠や全身の不調は、枕に原因があるかもしれない。
不適切な枕によって首が不自然な角度になると、首を通っている神経が圧迫されるからです。首が不自然な角度になっていると、首の回りの筋肉が緊張します。
すると、神経に栄養を運ぶ血管がしめつけられます。直接、神経を圧迫することはなくても、首が不自然な角度になっていると結果的に神経を傷めることになるのです。
首は脳と胴体を繋ぐ連結部であり、全身を司る大切な神経が集中しています。
その証拠に腕や足の骨を折っても死にはしませんが、首の骨を折ったら死んでしまいます。
この華奢な部位こそが、生命を維持し、健康を保つ重大なカギを握っているのです。
肩こりや腰痛、頭痛、手足のしびれ、四十肩や五十肩…私たちにはおなじみの体の不調にも、首の状態に端を発しているものがたくさんあります。
首の骨とは、全部で24個ある脊髄のパーツ(椎骨)のうち、頭と胴体をつなぐ7個の骨を指します。
首の骨も腰の骨も脊柱の一部であり、上から順に7個の頸椎(首の骨)、12個の胸椎、5個の腰椎、全部合わせて脊椎と呼んでいるわけです。
椎骨のなかには、脊髄神経という神経の束が通っています。
脊髄神経は全身の活動の要となっている神経。
椎骨は、この大切な神経を守っているのです。
束になっている脊髄神経は枝分かれして頸神経となり、頸の骨と骨のすきまから出て頭や頸、肩、腕に伸びます。
第一頸椎に枝分かれした頸神経は第一頸神経、第一頸神経そ第二頸神経の間に枝分かれした頸神経は第二頸神経という具合に、第一から第八までの頸神経が左右に細く長く伸び、全身の動きや感覚を司っています。
ですから、たとえば、親指を司る第六頸神経を痛めれば、親指に痛みやしびれが生じます。
頭部を司る第二頸神経を痛めれば、頭痛が生じます。
国民病と言われる肩こりも、じつは肩そのものの不調ではないことが多く、肩甲骨のあたりを司る第三頸神経や、第四頸神経が支障をきたした時に起こる症状なので、肩こりとは厳密にいえば「首こり」であることが多いのです。
つまり症状が出る場所はさまざまでも、もとをたどれば首に行き着くものが非常に多いのです。
さらには「頭が重い」「イライラする」「疲れやすい」といった、不定愁訴やうつ病など首とは関係ないように思える不調の根本原因が、じつは首にあったということも少なくありません。
このような仕組みを見るにつけ、首の重要性がよりリアルにわかるのではないでしょうか。
首を痛めることは、すなわち体中の動きや感覚を痛めるということ。逆に言えば、首を健康に保つことが、体全体の健康につながるのです。